Contact
お問い合わせ
業界や規模を問わず2000社以上の実績
まずはお気軽にご相談ください
人事組織に関するお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。
お役立ち資料を見る専門のコンサルタントがお客様の人事組織領域の課題解決をサポートします。
まずは相談する お電話でもご相談いただけます。
営業時間 9:00~17:30(土日祝を除く)

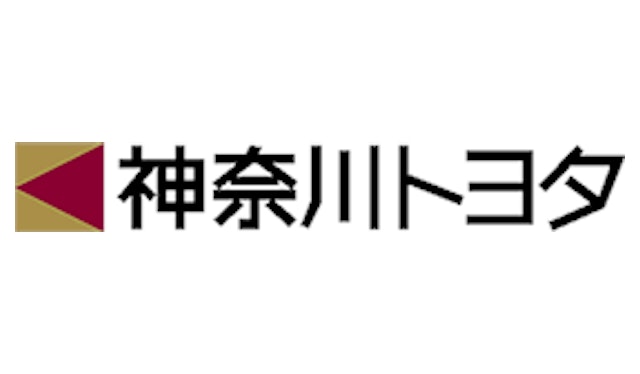
採用をサポートする社員に研修を実施 内定承諾率81%を実現
内定承諾率の上昇に向け営業社員と連携をした戦略的な採用活動の強化
私たちは、自動車の販売や整備をはじめ、
お客様個々のご要望に応える商品やサービスを展開しています。
創業から78年、単に車を販売するだけでなく、
理想のカーライフの実現をサポートする『くるま生活屋』としての仕事を追求してきました。
そのため、思いを同じくし、一緒に「真のくるま生活屋」を目指す仲間の採用は、
会社にとって特に重要な取り組みの一つであり、私たちは採用に役立つ情報を探していました。
様々な方と面会をし、多くの会社が自社のサービス紹介に終始するなか、
アチーブメントのコンサルタントは、私たちの話を丁寧に聞き、
本質的な課題を整理してくださいました。
そのなかで特に注目したのは、内定辞退の理由でした。
「会社の理念や考え方は共感できる」「採用社員に好感がもてる」という声がある一方で、
辞退者からは「実際にどんな職場でどのような人と働くのかイメージできない」という声もあったのです。
そのため、店舗で働く社員にも学生と関わってもらい、
会社の魅力や営業社員の生の声を届ける必要性を薄々は感じていたのですが、
営業社員への負担を考えて遠慮していたのです。
担当コンサルタントと話し合いを重ねるうちに、
「求める人材のレベルを落とさずに採用目標人数を達成するには、
営業社員の力を借りることが一番効果的だ」という結論に至りました。
そこで、実績をあげている営業社員の中から20名ほど選定し、
採用をサポートする社員を対象とした研修の導入に踏み切ったのです。
企業発展に向けた採用の重要性と学生との関わり方を学ぶ
研修のポイントは主に3つでした。
1つ目は、「採用活動が企業発展に与える影響を参加者に認識してもらうこと」です。
それも、単に参加者に説明する以上に、強く感じてもらう必要がありました。
そこで私たちは、役員の方々に研修のオブザーブに入っていただき、
さらには研修冒頭で登壇いただくという社内初の試みを通して、
「会社がどれほど採用に重きを置いているのか」を参加者に感じてもらう環境を整えました。
2つ目のポイントは、「企業目的と仕事の価値をより深く理解してもらうこと」です。
これに対しては、「お客様に提供できる価値」をテーマに、
参加者同士が自社の魅力について語り合う時間を設けました。
正直、最初は地味なプログラムだと感じていましたが、
講師の見事なリードにより、研修のなかで最も印象的な時間になりました。
というのも、成績優秀者ほど自社の魅力をそれぞれが感じているもので、
他の参加者の話を聞くなかで自分が気づいていなかった会社の魅力に気づき、
さらには、自分が伝えた魅力に周りからの共感が得られたことで、
その魅力に対する確信が深まっていったのです。
なかには、「自分は会社の魅力を伝えることができる」という自信まで醸成された参加者もいるようでした。
そして3つ目は、「学生への具体的な関わり方を体得してもらうこと」です。
会社の至らない部分を伝える際に、
どうしたら「欠点」ではなく「一緒に改善したい部分」として肯定的に伝えられるかなど、
参加者たちはロープレを交えて実践的に学んでいきました。
研修全体が参加者との双方向のコミュニケーションを重視し、
既に参加者の主体性が引き出されていたことが、ロープレを一層効果的なものにし、
ノウハウが参加者たちの腑に落ちていきました。
研修後、参加者たちから「採用は会社にとってすごく価値のある仕事だね」
「改めて神奈川トヨタで働いていてよかった」などの声をいただき、手ごたえを感じました。
また、実際に学生が店舗見学に参加した際には、
学生からの質問にサポート社員以外の店舗スタッフを交えて対応してくれるなど、
これまで以上の協力をしてくれるようにもなりました。
結果、学生からは「働くイメージが湧いたので神奈川トヨタに決めました」
「あの人のようになりたい」といった声をいただけるようにもなったのです。
営業社員からも「あの学生はこういうところが自社とマッチしている」
などといった報告が主体的にあがるようになり、
採用活動の参考となる情報の共有がよりスムーズになりました。
成果として特に注目すべきは、内定承諾率です。
店舗見学に任意参加した学生の内定承諾率は、
参加しなかった学生より15%も高く、81%という結果になりました。
また、採用基準を下げることなく、内定出し目標人数を180%超で達成。
日経産業新聞の一面にも掲載していただけました。
これらは、学生に営業現場を知ってもらうなかで、
会社の魅力や「一緒に働きたい」という社員の気持ちが伝わり、
私たちの会社に合った学生をたくさん採用できるようになった証拠だと思います。
たとえ採用担当者に営業経験があったとしても、
学生の目に映る私たちはあくまで「採用担当」だということが、改めて理解できました。
営業の現場について伝えるには、
店舗で働く社員の協力が欠かせないことが今回の取り組みで実証されたのです。
これからは入社後の育成も視野に入れながら、
営業社員の能力向上を通じて採用力を引き続き強化していきます。
お問い合わせ
業界や規模を問わず2000社以上の実績
まずはお気軽にご相談ください
人事組織に関するお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。
お役立ち資料を見る専門のコンサルタントがお客様の人事組織領域の課題解決をサポートします。
まずは相談する お電話でもご相談いただけます。
営業時間 9:00~17:30(土日祝を除く)