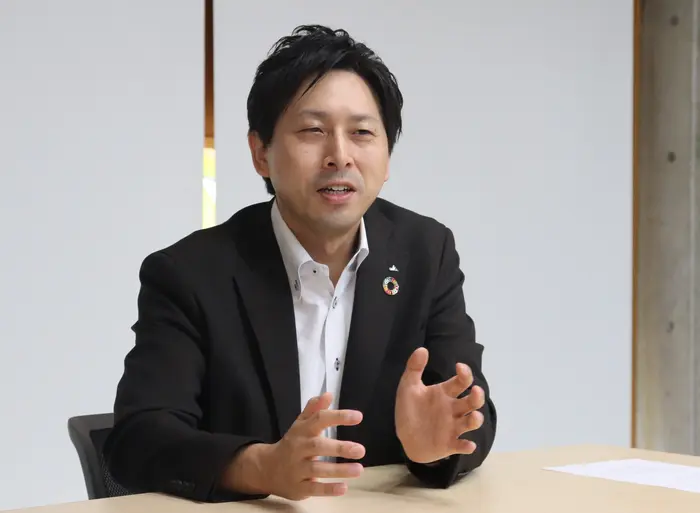Case Study
【さいたま農業協同組合様】キャリアデザイン研修

- 業種
- 農業生産に必要な購買事業、農畜産物の販売事業、営農サポート、金融、共済、高齢者福祉、旅行等
- 会社規模
- 1001名~5000名
- ご利用サービス
- キャリアデザイン研修
キャリアのピットインで、エンゲージメント低迷に打開策。
-
課題
中堅職員の「働きがい・モチベーション」が低く、キャリアを描けない
-
解決策
29歳、34歳、39歳の3階層に向けたキャリアデザイン研修を導入
-
成果
人生を豊かにするための学びを得て、主体的なアクションが生まれる

JAグループは"日本の「食」と「農」を守る"ことを使命に、農業生産に必要な購買事業や農畜産物の販売事業、営農サポートの他、金融、共済、高齢者福祉、旅行など幅広い事業を展開しています。その中でもさいたま農業協同組合(JAさいたま)様は「おもてなシンパシー」を合言葉に、地域に愛され信頼される組合として進化を続けています。
今回、29歳・34歳・39歳の3階層の職員様に向けたキャリアデザイン研修をご支援させていただきました。導入の背景や成果について、人事部人事企画課の遠藤様と岸様にお話をお伺いしてきました。
-
JAさいたま 人事部人事企画課課長 遠藤 様(上写真:左)
-
JAさいたま 人事部人事企画課係長 岸 様(上写真:右)
(以下:敬称略)
農業の変革期を迎える今、守りたい精神がある。
貴組合の成り立ちや事業内容についてお聞かせいただけますか?
遠藤:JA(Japan Agricultural Cooperatives:農業協同組合)の歴史は明治時代の産業組合を前身として、 戦後1947年制定の農業協同組合法に基づき設立がなされました。日本全国に展開しており、農家を中心とした地域住民が組合員となり、相互扶助の精神で農業と生活を支える協同組織です。JAさいたまは2000年に誕生。その後、2016年に広域合併をしてさいたま市を含む9市1町を管轄しています。南北約48km・東西約20kmに及ぶ総土地面積は43,230ha、人口は約270万人で県人口の36.9%を占めており、県内で最も都市化が進んだ地域でJAを運営しています。
事業内容については「ゆりかごから墓場まで」をコンセプトに、人の一生におけるそれぞれのライフステージに合わせて、全てに寄り添える総合事業を行っています。農家の皆様を助けるということはもちろん、農業にまつわる人々の暮らし全てを支援することを大切にしています。
市場や環境の変化について感じていることはありますか?
岸:農業者の減少が特に顕著になっています。江戸時代では国民の80%が農家で自給自足を行っていたところから、現在では日本人口の1%にまで縮小しており年齢層も益々上がっています。"日本の「食」と「農」を守る"をどのように実践していくのかという課題と直面していますね。昔は農家の皆様もJAを頼ってくれていましたが、現在は業者も多くなり選択肢が増えています。
ただ、ある印象的なエピソードとして、借入を行う際に金利がJAよりも安い銀行があったにも関わらず、JAに決めているという農家様がいらっしゃいました。その理由を聞いたところ、「銀行はお金を貸してくれるかもしれないけれど、農業の支援はしてくれないからね」とおっしゃっていました。私たちはどこまでも農家に寄り添い、農家を大事にするという根幹を見失わずに、農業の変革期を乗り越えていきたいと思っています。
ありがとうございます。JAさいたま様での人材育成はどのように行っていらっしゃるのでしょうか?
遠藤:以前は管理部の中に人事教育課がありましたが、約1000人の職員がいるので労務管理に追われる中で、戦略的な人事ができないという課題がありました。そこで人事部を創設し、人事企画課という課を立ち上げて、現在採用や教育を担っています。
岸:私は昨年に人事企画課に配属となり、使命感を持って人材育成に取り組んでいます。これまでも階層別研修はずっとやってきていましたが、職員にとって「受けて終わり」「研修内容を現場に活かすことができない」といった研修も多々あり、前年踏襲の打破をしたいと思っていました。JAとしての研修で必須のコンテンツは継続しつつも、やるのであれば職員が受け身ではなく、楽しみながら主役になれる研修をやりたいと思い描いていました。
受講者が「主役になれる」研修をやりたかった。
アチーブメントHRソリューションズとの出会いのきっかけを教えていただけますか?
岸:私自身、研修を企画する上でただいるだけの研修にはしたくないと思っていましたし、しっかりと効果性がある研修を実施したいと思っていました。そこで昨年4月~9月の6か月間は、数多くの企業のセミナーに参加しました。1日のスケジュールすべてがセミナーで埋め尽くされた日もあったぐらい、気になった内容のものは全て受講しました。
その時に日本の人事部のサイトで「~場当たり的な研修企画から戦略的な研修企画へ~行動定着率80%を実現する研修企画・設計方法」という御社のセミナーを見つけて申し込みをしたのが出会いのきっかけでした。そしてコンサルタントの方と対話を重ねながら、12月に実際のコンテンツの体験ができる「キャリアデザイン研修体験セミナー」を受講いたしました。
組織のエンゲージメントと個人のキャリアは、表裏一体。
キャリアデザインについて、研修導入前、課題に感じていたことがあったのでしょうか?
遠藤:実は昨年2024年11月に実施したエンゲージメント調査において、JAさいたまは全国の農業協同組合の平均よりもエンゲージメントが低いという結果が出ていました。過去5年間のエンゲージメント調査と比較しても、特に30代の職員の「やりがい」「モチベーション」の項目が低く、若手・中堅層がキャリアを描けないという現状があることに大きな課題を感じました。
そして12月に実施した自己申告の中で「あなたが描いているキャリアを書いてください」という項目を追加しましたが大半の職員が空白で、自身のキャリアに対して目標を持てないということが浮き彫りになり、キャリアデザイン研修を実施する根拠となりました。
アチーブメントHRソリューションズの研修導入の決め手になったものは何でしたか?
岸:初めて御社のセミナーを受講した時に、基礎理論となっている選択理論®心理学に納得できたことが大きかったです。自分自身も14年間JAに勤めていて、ずっとモチベーション高く楽しくやってきたかと言うとそうではなくて、辛い経験もしたり、異動によって様々な部署も経験したりしてきました。セミナーに参加している中で気づいたことが、モチベーションが低い時というのは、どこかで周りのせいにしていたなということでした。
JAさいたまでは、2018年より発足した組織基盤強化プロジェクトチーム「自己改革"未来へJANP"(ジャンプ=JAさいたまNew Project)」(以下:JANP)という、若手職員が中枢となる組織基盤強化プロジェクトチームがあります。発足当時、私がJANPに参加した背景には組織をより良くしていくためには自分が変えていかなければという熱い想いがあり、メンバー、サブリーダー、リーダーを合計6年間務めていました。そこが「自分自身が変わらなければ、周りも変わらない」という選択理論®心理学の内的コントロールの価値観に一致しており、共感できたポイントでした。
遠藤:セミナーやミーティングを通してあらゆる会社を見た岸から会ってほしいと言われたアチーブメントHRソリューションズは、初めて会った時から教育に対する熱い想いを持っている会社だと思いました。担当コンサルタントの方からは、選択理論®心理学にもとづく研修プログラムが本当に良いものだと心から思っていることが伝わってきました。
そして何よりアチーブメントグループとしてのブランドが信頼の証になっています。Great Place To Work®が主催する「働きがいのある会社ランキング」で1位を獲得していること、メジャーリーガーの大谷選手の出身校である花巻東高校の教育プログラムを手がけていることなど、数々の実績がある企業が研修をしてくれることを、職員も喜んでくれています。全国のセミナーでも発表の折には、御社の名前を出しましたし、自信を持って進めたいと思っています。
節目となる年齢の手前で、キャリアのピットインを。
ありがとうございます。実際の研修の中で印象に残っている体感型ワークや学びのセッションはありますか?
岸:中堅職員のキャリアデザインに課題がありましたので、定期的にピットインのタイミングを作るべく、29歳、34歳、39歳の3階層に向けたキャリアデザイン研修を実施いたしました。この年齢にした理由は、節目となる30歳、35歳、40歳になる一歩手前で自身のキャリアについてじっくりと考える時間を持てるようにしたかったからです。3階層合計で60名の職員が受講をしました。
私自身も同世代なので実際に受講もさせていただいた立場として、すべて深い気づきが得られるものばかりでしたが、一番印象が強いのはレゴワークです。お題は「理想の職場」をレゴで表現するというもので、周りも最初はどうやって作ればいいのか悩んでいました。ある意味、子どもの頃の気持ちを思い出さないとできなかったりして、それでも潜在意識で手を動かしていくうちに完成したものは、本当に全員の作品が素晴らしかったです。研修を企画していた時、おもしろいと思ってもらえることをやって、それを現場に持ち帰って実現に向けて考えて行動できるようにしたいと思っていたので、まさにぴったりのワークだったと思います。
遠藤:やっても意味がないと決めつけるのではなく、まずはやってみることで次に繋がりますよね。誰もが何かしら自分の中で思っていることがあり、言語化できないものを表現できるのがレゴワークであると感じることができました。
岸:39歳の階層においては、管理職になっている方から一般職の方まで役職も様々であったり、ライフステージもばらつきがあったりと、様々な環境にいる職員が一緒に研修を受けることで良い刺激になったと思います。特に5つの基本的欲求の学びのセッションは、自分を満たすと同時に、他者と良好な人間関係を築く上で全職員が受けるべきというコメントが多数寄せられました。
人生を豊かにする、今の自分が在ることを肯定する。
講師との関わりやお話の中で、最も気づきになったことはありましたか?
岸:講師の方はそれぞれのワークやセッションについて、すべてなぜやったのかということを丁寧に伝えてくれるので納得感が大きかったです。
遠藤:私も後ろから見ていましたが、3階層とも全員が真剣に講師の話を聞いていましたし、うなずきが深かったです。キャリアデザイン研修は仕事や組織の中だけの自分にフォーカスするのではなく、プライベートの自分も含めて人生を考える機会になります。だからこそ、今までなかなか考える機会のなかった職員も「自分がどうなりたいのか」ということを見つめ、講師の話を聞く中で「人生を豊かにするための学びが得られた」という声が多く聞かれました。
岸:特に、話の中での例え方が上手だと思いました。年齢を重ねることの意義を説明する際には山に例えて、山のふもとにいる時には見えなかったものが見えるようになること、高さによって見える景色が変わることなど、なるほどと思うことが沢山ありました。人生の様々な出来事を振り返る中で、だから今の自分が在るということを肯定することができました。
ありがとうございます。研修実施から2か月が経ち、受講者の皆様にはどのような変化がありましたか?
遠藤:大きな一歩は「気づいてもらえたこと」です。漠然と毎日を過ごしていた職員が少なからず目標を見つけてくれたこと、そして目標の土台になっている人生の目的を見つけて、そのための目標であることに気づいてくれたことこそ、大きな変化の礎になっていくと思います。
今回の研修後、受講者の中から「JANP」に名乗り出てくれた方がいらっしゃいます。もともと「JANP」は広域合併をした際に、JAさいたまをより良くしていきたいというムーブメントが結集して発足した手上げ制のプロジェクトです。私自身も本店部署として参加し、もともと「人の内面を変えたい」と思っていたので、人事企画課として裁量を持った時には水を得た魚のように躍動したのを覚えています。同じように、今回の研修を受講した職員の中から「自分が動かなくては始まらない」と思って行動してくれたことはとても嬉しい変化です。
岸:自分自身が30代のど真ん中にいるのでわかるのですが、仕事としても忙しさが増し、頑張らなくてはいけない世代なので、自分のことで一杯一杯になりやすい時期です。周りを見ることを忘れてしまったり、恩送りをしたいと思っていてもなかなか手がつけられなかったり、いつの間にか「働きがい」が見えなくなってしまうということが誰しも起こり得ると思います。
今年のエンゲージメント調査の結果が出るのはこれからになりますが、今回の研修で各自が社会人になってからのモチベーションの推移を数値で可視化し、グループワークで振り返りを行うことによって、自分自身の働きがいやモチベーションの源泉を思い出すことができたことはとても良い兆しになっていると思います。
JAグループのエンゲージメントを底上げする、第一人者として。
今後、お2人が目指していることや新たにチャレンジしていることを教えてください。
遠藤:私は、JAを心から良いと思ってもらえる職員を育てること、そしてJAグループのエンゲージメントを底上げする第一人者になるということを成し遂げていきたいと思っています。現在7期目になるJANPの取り組みは、過去幾度も日本農業新聞の全国版にも取り上げてもらっています。私たちの数々の挑戦がJA全体の底上げに繋がると信じています。研修だけではなく、トータルでエンゲージメントを高める施策によって、自信を持って自分の職場を薦めたいと思えるJA職員を増やしていきたいですね。
先日、御社の人事イベントに参加した際、「あなたが創り出したい理想の組織とは?」を言語化して紙に書いて集合写真を撮ったことが思い出深くて、実はJAさいたま全体でも実践しています。今後も継続することによって、職員全員が当事者意識を高め、和気あいあいと楽しんで組織の未来を考える文化を醸成していきたいと思っています。
岸:私は今回、事務局でもあり受講者でもあるという立場から、改めて「キャリアとは自分がつくるものであり、それが環境をつくり、主体性を持った組織になっていく」ということを実感しました。他者に委ねるのではなく、自分自身が創り出していく重要性を全職員に広めていきたいです。それが結果的にエンゲージメントを向上させる原点であると思います。
そしてJAだけではなく、全国レベルで有名な組織にしていきたいと思っています。JAが守り受け継いできた相互扶助・利他の精神が全国に波及していくことを願っています。
最後に、JAグループの発展に情熱を燃やし尽力していらっしゃるお2人のモチベーションの源泉を教えてください。
岸:私は元来、自分がどんなに疲れても、周りが楽しんでくれたら何でもやりたいと思う性格で、現在の企画職に結びついているのだろうと思います。そして、自分の考えを認めてもらえている環境に感謝し、これからも企画を具現化していきたいと思っています。
遠藤:私の原動力は、自分に関わった全ての人に幸せになってもらいたいということ。役職が上がって関わる人が多くなっている今だからこそ、エンゲージメントは是が非でも良くしていきたいと心に決めています。
Cases関連する事例
サービスをご検討中の方
業界や規模を問わず、まずはお気軽にお問い合わせください。
- ・アチーブメントHRソリューションズの特色を知りたい
- ・自社に適した会社・サービスなのか知りたい
- ・まずは課題感を聞いてほしい